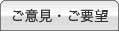『擬態』
テーマ:園内の野生生物 投稿日:2016年9月15日
こんにちは。
動物たちのエサの収穫に園内をうろうろしている小動物担当です。
サル舎の壁に止まっていたとのことで、こんな昆虫がやってきました。

ひょろひょろっと、とてもスマートな体と脚。
ずばり、この昆虫はナナフシの仲間のタイワントビナナフシといいます。
初めて園内で見つけたので、ちょっぴり興奮しました。
このナナフシは、夏〜秋にかけて成虫が現れるので秋のナナフシといえるかもしれません。
たしかに、体の色も秋色な感じがします。(なんとなくです)
.jpg)
名前に「トビナナフシ」と付くくらいなので、ちゃんと羽があります。
羽は薄いピンク色をしていて、飛ぶこともできます。
このように少しイジワルをすると、ゴボウのような不思議なにおいを出すのも特徴のひとつです。
ちなみに、こちらのタイワントビナナフシは外来生物といわれています。
国外では、中国、台湾、東南アジア、国内では本州、九州、南西諸島などに生息しています。
日本の本州の個体群について古い記録がなく、卵を植物に付着させる方法で産卵するため、海外や本州以外の国内から植物などを移入した際に、一緒に卵も入ってきた可能性が考えられています。
(2).jpg)
ちなみにちなみに、ナナフシの仲間の多くが単為生殖という繁殖の方法をしています。
単為生殖って?????かもしれませんが、簡単にいえばクローンなのです。
母メスは、オスと交尾しなくても、お腹が大きくなり産卵をして、卵から生まれてきた子どもたち(全てメス)は母のコピーで、またオスがいなくてもお腹が大きくなり…という不思議なサイクルで生活をしています。
このタイワントビナナフシも例外ではなく、クローンな繁殖方法をしています。
その為、このタイワントビナナフシはメスしかいないということなんです。
で・で・で・ですが、とても不思議なことにオスはいままでに1頭だけ見つかっているという不思議さしか残らない昆虫なのです。
(2)(3).jpg)
うーん、ナナフシって不思議ですよね。
園内には、展示動物だけではなく野生の小さな動物もたくさん見ることができます。
展示している動物を観察するときに、足下や葉の上、動物舎の壁などにもご注目していただけると、何か面白い発見があるかもしれませんよ。
動物たちのエサの収穫に園内をうろうろしている小動物担当です。
サル舎の壁に止まっていたとのことで、こんな昆虫がやってきました。

ひょろひょろっと、とてもスマートな体と脚。
ずばり、この昆虫はナナフシの仲間のタイワントビナナフシといいます。
初めて園内で見つけたので、ちょっぴり興奮しました。
このナナフシは、夏〜秋にかけて成虫が現れるので秋のナナフシといえるかもしれません。
たしかに、体の色も秋色な感じがします。(なんとなくです)
.jpg)
名前に「トビナナフシ」と付くくらいなので、ちゃんと羽があります。
羽は薄いピンク色をしていて、飛ぶこともできます。
このように少しイジワルをすると、ゴボウのような不思議なにおいを出すのも特徴のひとつです。
ちなみに、こちらのタイワントビナナフシは外来生物といわれています。
国外では、中国、台湾、東南アジア、国内では本州、九州、南西諸島などに生息しています。
日本の本州の個体群について古い記録がなく、卵を植物に付着させる方法で産卵するため、海外や本州以外の国内から植物などを移入した際に、一緒に卵も入ってきた可能性が考えられています。
(2).jpg)
ちなみにちなみに、ナナフシの仲間の多くが単為生殖という繁殖の方法をしています。
単為生殖って?????かもしれませんが、簡単にいえばクローンなのです。
母メスは、オスと交尾しなくても、お腹が大きくなり産卵をして、卵から生まれてきた子どもたち(全てメス)は母のコピーで、またオスがいなくてもお腹が大きくなり…という不思議なサイクルで生活をしています。
このタイワントビナナフシも例外ではなく、クローンな繁殖方法をしています。
その為、このタイワントビナナフシはメスしかいないということなんです。
で・で・で・ですが、とても不思議なことにオスはいままでに1頭だけ見つかっているという不思議さしか残らない昆虫なのです。
(2)(3).jpg)
うーん、ナナフシって不思議ですよね。
園内には、展示動物だけではなく野生の小さな動物もたくさん見ることができます。
展示している動物を観察するときに、足下や葉の上、動物舎の壁などにもご注目していただけると、何か面白い発見があるかもしれませんよ。
『アオマツムシ』
テーマ:園内の野生生物 投稿日:2016年9月13日
こんにちは。
今回は「ふくちゃん」展示場前の芝生広場からお送りします。
小動物担当です。
芝生広場に、こんなものが隠れていました。
(2)(3)(4).jpg)
アオマツムシです。
このアオマツムシ、園内でも木で休んでいることをよく見かけることのできる昆虫です。
8月〜11月頃に成虫として現れるため、秋の昆虫のひとつといえるかもしれません。
いつ見ても、きれいな黄緑色をしています!
(2)(3)(4)(5).jpg)
この個体は、葉のすき間に上手に隠れていますね。
このように、木の上での生活がメインな昆虫です。
ちなみに、こちらのアオマツムシですが、立派な外来生物です。
中国原産と考えられていて、明治時代に東京で見つかって以降、都市部を中心に分布を拡大しています。
(2)(3)(4)(5)(6).jpg)
「リーリーリー♪」ときれいな声で鳴くのが特徴ですが、この大合唱が騒音被害とされることもあるアオマツムシ。
今日も良いものが見れました。
ふと横を向くと、ふくちゃんがゆっくりのんびりしていました。
今回は「ふくちゃん」展示場前の芝生広場からお送りします。
小動物担当です。
芝生広場に、こんなものが隠れていました。
(2)(3)(4).jpg)
アオマツムシです。
このアオマツムシ、園内でも木で休んでいることをよく見かけることのできる昆虫です。
8月〜11月頃に成虫として現れるため、秋の昆虫のひとつといえるかもしれません。
いつ見ても、きれいな黄緑色をしています!
(2)(3)(4)(5).jpg)
この個体は、葉のすき間に上手に隠れていますね。
このように、木の上での生活がメインな昆虫です。
ちなみに、こちらのアオマツムシですが、立派な外来生物です。
中国原産と考えられていて、明治時代に東京で見つかって以降、都市部を中心に分布を拡大しています。
(2)(3)(4)(5)(6).jpg)
「リーリーリー♪」ときれいな声で鳴くのが特徴ですが、この大合唱が騒音被害とされることもあるアオマツムシ。
今日も良いものが見れました。
ふと横を向くと、ふくちゃんがゆっくりのんびりしていました。
『今日のふくちゃん 23』
テーマ:ボルネオゾウ 投稿日:2016年9月11日
今日は外に出てすぐ、おもむろにエサのバショウを鼻で持ち歩き、
何のちゅうちょもなく、ヒョイっとバショウを置きました。
細い棒の上に!!
(2)(3)(4)(5).jpg)
置き直したりしてません!!
たった1回!!
しかも、そろーっとではなく、テクテクと歩き、パッと置きました!!
鼻で持った時点で、重心がどこにあるのかわかるのかもしれません。
改めて、「ふくちゃん」の、そしてゾウの感覚の良さに驚かされました!!!
置かれたバショウは、その後おいしくいただいたようです。
(2)(3)(4)(5)(6).jpg)
何のちゅうちょもなく、ヒョイっとバショウを置きました。
細い棒の上に!!
(2)(3)(4)(5).jpg)
置き直したりしてません!!
たった1回!!
しかも、そろーっとではなく、テクテクと歩き、パッと置きました!!
鼻で持った時点で、重心がどこにあるのかわかるのかもしれません。
改めて、「ふくちゃん」の、そしてゾウの感覚の良さに驚かされました!!!
置かれたバショウは、その後おいしくいただいたようです。
(2)(3)(4)(5)(6).jpg)
『子煩悩 大伯母 マユミ』
テーマ:カピバラ 投稿日:2016年9月9日
先日、「しろとり」が4頭出産し「フクタ」や「マユミ」も子育てをサポートしていることをお伝えしたかと思います。
.jpg)
父親の「フクタ」と母親の「しろとり」が子育てするのは、なんとなくわかる気がしますが、「マユミ」は?
どんな関係性??と、疑問に思う方もおられるかもしれませんので、ここで一度整理します。
今回、「フクタ」と「しろとり」の間に子どもが生まれました。
「フクタ」の父は「かん太」で母は「ウタネ」。
「マユミ」と「かん太」と「ウタネ」は異母兄弟で、「マユミ」は一番年上です。
つまり、フクタにとっては伯母にあたり、子ども達にとっては大伯母にあたります。
「マユミ」は子どもを産んだことがありませんが、子育ての経験はバッチリあります。
そのせいもあってか、「マユミ」は、「しろとり」からも、子ども達からも信頼されているようで、子ども達は「しろとり」よりも「マユミ」と一緒にいることの方が多い気がします。
「しろとり」も安心しているのか、こどもを「マユミ」に預けて、昼寝してたり、ご飯食べたりしています。
(2).jpg)
(「マユミ」と子ども、奥にしろとりのお尻)
(2)(3).jpg)
(「マユミ」の前で寝る子ども達)
もちろん、授乳は「しろとり」しかできませんので、頑張って授乳をしていますが、
間違えて、「マユミ」に吸い付く事もあります。
(2)(3)(4).jpg)
(上が「マユミ」、下が「しろとり」)
吸い付かれた「マユミ」は毛が逆立っていました。
群れにとって「マユミ」は本当に良い存在になっています!!
なんだか家族っていいですね~!
「マユミ」さん! 勉強になります!!
ふくず~のカピバラ家族を観察するべし!!!
.jpg)
父親の「フクタ」と母親の「しろとり」が子育てするのは、なんとなくわかる気がしますが、「マユミ」は?
どんな関係性??と、疑問に思う方もおられるかもしれませんので、ここで一度整理します。
今回、「フクタ」と「しろとり」の間に子どもが生まれました。
「フクタ」の父は「かん太」で母は「ウタネ」。
「マユミ」と「かん太」と「ウタネ」は異母兄弟で、「マユミ」は一番年上です。
つまり、フクタにとっては伯母にあたり、子ども達にとっては大伯母にあたります。
「マユミ」は子どもを産んだことがありませんが、子育ての経験はバッチリあります。
そのせいもあってか、「マユミ」は、「しろとり」からも、子ども達からも信頼されているようで、子ども達は「しろとり」よりも「マユミ」と一緒にいることの方が多い気がします。
「しろとり」も安心しているのか、こどもを「マユミ」に預けて、昼寝してたり、ご飯食べたりしています。
(2).jpg)
(「マユミ」と子ども、奥にしろとりのお尻)
(2)(3).jpg)
(「マユミ」の前で寝る子ども達)
もちろん、授乳は「しろとり」しかできませんので、頑張って授乳をしていますが、
間違えて、「マユミ」に吸い付く事もあります。
(2)(3)(4).jpg)
(上が「マユミ」、下が「しろとり」)
吸い付かれた「マユミ」は毛が逆立っていました。
群れにとって「マユミ」は本当に良い存在になっています!!
なんだか家族っていいですね~!
「マユミ」さん! 勉強になります!!
ふくず~のカピバラ家族を観察するべし!!!
『今日のふくちゃん 22』
テーマ:ボルネオゾウ 投稿日:2016年9月7日
タイヤ大好き「ふくちゃん」。
2個使いが定番になってきました。
以前はタイヤ1つを立ててお腹でつぶしていましたが、
最近は1つを台座に、もう一つをその上に置いてつぶします。

こだわりがあるようで、
良い位置になるように、鼻で何回か置き直して微調整します。
「ふくちゃん」にとってベストな位置が写真の状態のようです。
ひとそれぞれこだわりがありますが、ゾウもなのかもしれませんね。
2個使いが定番になってきました。
以前はタイヤ1つを立ててお腹でつぶしていましたが、
最近は1つを台座に、もう一つをその上に置いてつぶします。

こだわりがあるようで、
良い位置になるように、鼻で何回か置き直して微調整します。
「ふくちゃん」にとってベストな位置が写真の状態のようです。
ひとそれぞれこだわりがありますが、ゾウもなのかもしれませんね。